|
上部・基礎構造の設計 |
| 上部構造の設計は(8)式の層せん断力係数に対して許容応力度設計を行うことになっている。 |
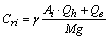 |
(8) |
|
| ここで、 γ は免震部材のばらつきなどを考慮した係数で1.3以上となっている。 Qh , Qe は基準変位時のダンパー、アイソレータそれぞれの負担せん断力である。(8)式において Ai 分布による増幅はダンパーのせん断力だけに関係している。これはアイソレータのせん断力は上部構造で増幅しないことが、既往の研究(例えば文献5))で判明しているためである。また、上部構造の層間変形角は1/300以下とされているが、本当の免震構造であれば更に小さな層間変形角を十分達成できるはずである。 |
|
基礎構造の設計せん断力係数は次式で求める。免震層のせん断力に地下震度0.2を加えて計算する。 |
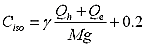 |
(9) |
|
| その他の検証 |
| その他の規定としては、ダンパー降伏後の接線剛性 Kt に対応した周期(接線周期) Tt が2.5秒以上、ダンパーの負担せん断力 μ が建物重量の3%以上、免震層の偏心率が0.03以下など。 |
アイソレータ軸力に関して、転倒モーメントによる変動軸力と鉛直震度0.3を考慮して算出した鉛直荷重が0以上、すなわち引張力は作用させないこと、最大圧縮力は鉛直基準強度 FC 以下となることが規定されている。積層ゴムに引張が作用するような高層免震の設計では、ここで説明している告示計算は適用できないので、時刻歴解析を用いた検証を行う必要がある。
|
| 免震材料 |
| 免震部材(アイソレータ、ダンパー)は告示2010号により指定建築材料に追加された。本基準では免震部材の満たすべき必要な特性を定めている。当面は全ての免震部材が指定建築材料としての認定を受けなければならない。 |
| 本来、免震部材は構造部材であり、「材料」ではない。材料として規定されたため、告示2009号では材料強度や許容応力度といったおかしな規定が生まれることになる。免震部材の認定は荷重支持性能、変形性能、エネルギー吸収性能などが実験データに基づいて確認され基準値が決定される。構造計算にはこれらの基準値が使用される。部材の性能・仕様を決めることは本来設計の一部である。認定では免震部材の設計を行っていることになるにも関わらず、設計責任が曖昧となっている。また、旧38条による評定とは異なり部材認定ではできるだけ一般的なデータが求められるため、新しい部材の開発・使用が難しくなっている。 |
| 鉛直基準強度は告示2010号で規定される圧縮限界強度に基づいて設定される。圧縮限界強度とは、アイソレータが座屈や破断をすることなく安全に支持できる圧縮応力度と規定され、 |
鉛直基準強度 FC  圧縮限界強度×0.9 圧縮限界強度×0.9 |
| となっている。鉛直基準強度は材料強度に等しい。水平基準変形 δU は鉛直基準強度 FC の1/3に相当する荷重を支持した状態での水平限界変形となっている。 |
| 文献3)では認定材料の基準値一覧が示されている。本資料より同種の積層ゴムについて限界性能を比較すると、せん断ひずみの小さい領域では限界面圧の違いは大きいものの、限界変形付近の特性は類似している。特に最大変形能力は全てがせん断ひずみ400%で一致している。水平基準変形がせん断ひずみ400%とすれば、設計限界変位は320%(=0.8×400%)となる。これと応答変位が一致するとすれば、基準変位は最大で240%(=320%/1.32)となる。このせん断ひずみは2次形状係数が5の積層ゴムでは、直径のほぼ半分以下の変形に相当する。 |
問題は何をもって限界としているのか、その時の履歴曲線の状態はどうなっているか、実験データの信頼性、スケール効果は、メーカー間の評価法の統一は計られているのか等についてデータが開示されることが、正しい部材性能を認識する上で非常に重要であると考えている。また、告示2010号の性能評価項目には、積層ゴムの面圧依存性、減衰性能を有する積層ゴムでは重要と思われる速度依存性、繰り返し依存性などの重要な評価項目が明記されていない。性能評価が不十分な告示で正しい部材性能を認識できるはずはないと思われる。最も大切なことは、設計者自身が免震部材の性能を正しく評価し、不十分なデータがあれば追加試験などを強く求めることである。
|
|
1質点系モデルでの応答検証 |
| 解析モデルは1質点系モデルで免震層の復元力特性はバイリニア型とした。アイソレータは弾性で、水平剛性に対応する周期 Tƒ ( Tt に同じ)を2〜6secまで変化させた。ダンパーは完全弾塑性型とし、降伏荷重は質点重量に対して αs =3,5,10,15%とした。降伏変位は1.0cmで一定である。粘性減衰は考慮していない。 |
|
設計限界変位 δS を適当に設定すれば、(1)式から(7)式を使って、応答変位 δr を自動的に求めることができる。そこで、限界変位を1cm刻みに変化させたときの応答変位との関係を図5に示す。係数 α は1.2、周期 Tƒ は4.0secで、Gs=1.0と2.025の場合である。 δr = δS となる点が等価線形化法の収束値(図中の対角線)であり、それより右側が応答の判定を満足する領域となる。Gsが1程度では応答変形はそれほど大きくはならないが、Gsが2前後では応答変位は1mを越える。このような場合、応答変位を減少させるためには、免震周期を短くするか、ダンパー量を増やすかしかない。 |
| 一般的に免震周期を短くすれば、免震層の応答は小さくなると思われるが、告示式に従うと、周期を3秒から6秒まで変化させても不思議なことに応答変位と限界変位の関係は全くと言っていいほど変化がない。このため、免震層の応答変位を小さくするにはダンパー量(減衰)を増やすしかない。告示にはダンパー量に対する制限はないため通常の免震構造では考えられないところまで増やすことを可能としている。これでは、耐震構造に近い免震構造ができあがってしまう。 |
| 図6には1質点系モデルの周期 と地震応答変位の関係を描いている。入力波にはBCJ-L2波の振幅を0.8倍から2倍まで、およびEL CENTRO(NS)波と八戸(NS)波の最大速度を25cm/sから125cm/sまで5段階に変化させた波を用いた。加えて同図中には図4と同様の手法を用いて告示式から計算した基準変位をGs毎に示している。地震応答解析結果は免震周期の違いにより最大変位が変化するのに対し、告示式の応答は周期の影響を受けずほぼ一定の変位を保っている。同図から、Gsごとに地震波のレベルを対応させるとすれば、Gs=1はEL CENTROや八戸では50kine相当、BCJ-L2では0.8倍相当、Gs=2ではそれぞれ100kine、1.6倍相当と言える。 |